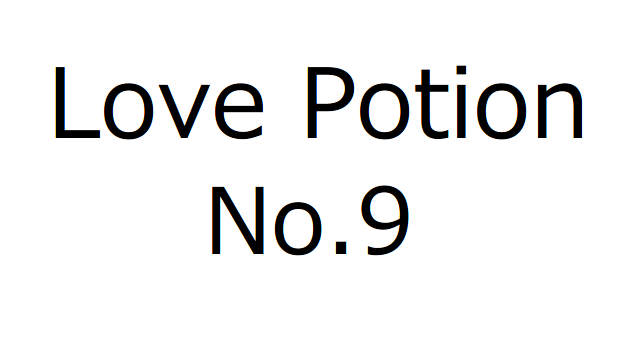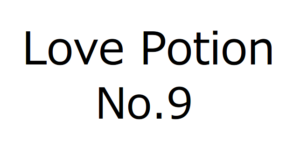君は朝起きた時に、見ていた夢を覚えているだろうか。
覚えていることもあるし、全く覚えていないこともある、というのが大勢であろう。
どういう時に覚えていて、どういう時に忘れてしまうのか。はたまた夢を見ていない時もあるのか。
夢や人間の脳のメカニズムについては解明されていない事も多いようなので、ここであれこれ筆者の頼りない推論を展開するつもりはない。
これはある男の見た夢のお話である。
ある朝、男は昨晩の夢をはっきり覚えていた。夢の中で「惚れ薬」の製法を発明し、実際に作り、女の子に飲ませて愉しむという幼稚なことおびただしい夢であった。
「おい、面白い夢をみたよ。」
男はおはようの挨拶もせぬうちに、妻に言った。
「あら、どんな夢?」
「うん、オレが惚れ薬を発明してね。いろんな女の子に飲ませる夢さ。」
「まあ、いやらしい。」
妻はそう言って屈託なく笑っていた。男の頭の中にはその惚れ薬の製法が完全に残っている。
ちょっとした興奮状態にあった男は、聞かれもしないのにその製法を妻に説明し始めていた。
「いや、それがそんなに難しくないんだよ。いいかい、まず温かいミルクをコップ一杯。それから松の木の皮を削った粉を少々。犬の小便をスプーン一杯。最後に俺の涙で完成だ。」
「あら、すぐ作れそうね。」
妻は朝食の用意をしながら、適当に応答していた。
「さて、散歩に行ってくるよ。アンナ、おいで。今日は海の方に行こうね。」
犬の散歩は男の日課である。いつもは歩きにくいので浜辺などには行かないのだが、そこに繁茂する松の木が目的であった。
「ただいま。この散歩で一気に二つも材料が手に入ったよ。」
男が手にしている木の皮と、なにやら容器に入った液体を見て妻はぎょっとした。
「ちょっと、あなた本当に作る気なの?」
「まあ、簡単なんだ。すぐできるよ。ミルクをあっためておくれ。」
持ち帰った松の木の皮をヤスリで削ってミルクに入れ、アンナの小便と思しき液体をスプーンで正確に一杯計って入れた。
「よし、あとは俺の涙か。死んだばあちゃんのことを思い出してもいいんだが・・・玉ねぎはあったかな?」
言い出すときかない男の性格を知っている妻は、おとなしく玉ねぎを出してきた。 男は台所に行くと、包丁で玉ねぎをきざみ始めた。わざと目を大きく見開きながらだ。するとすぐに目を開けていられないくらいの刺激で、涙が溢れ出した。
「よしよし、これで完成だ。」
「誰が飲むの?」
「おまえ、飲んでみてくれよ。」
「いやよ、アンナのおしっこが入ってるじゃない。それに自分の奥さんに惚れ薬を飲ませるなんて、そんな馬鹿な話ないわ。」
「それもそうだな。しかし、これは売れるぞ。製法を特許にしたら億万長者だ。」
「そうね、本当に効くならね。」
妻はそう言って朝食の後片付けを始めたが、もう笑顔はなかった。
「よし、ちょっと薬屋に行ってくる。」
男はコップに入った液体を持って、丘の上にある薬屋に出かけて行った。
「おう、おやじ。すごい薬を発明したんだ。店に置けば絶対儲かるぞ。」
「へえ、一体何の薬だい?」
「聞いて驚けよ、惚れ薬さ。」
「はは、そりゃすげぇや。で、誰かに試したのかい?」
「いや、まだだ。でも効くはずさ、夢の中では証明済みだ。」
「なんでぇ、夢じゃダメだよ。」
「よし、ちょっと待ってろ。」男は薬屋を出て、幼なじみの女の家に向かった。
「よお、この薬飲んでくれないかな。」
「何のお薬?」
「惚れ薬なんだけど。」
女は頬を紅潮させながら言った。
「駄目よ、意味ないわ・・・だって私、あなたのこと・・・」
男は踵を返し、馴染みの酒場に向かっていた。昼間は喫茶店として営業しており、そこの女給とは顔なじみなのだ。
「よお、この薬飲んでくれないかな。」
「何のお薬?」
「惚れ薬なんだけど。」
女は頬を紅潮させながら言った。
「駄目よ、意味ないわ・・・だって私、あなたのこと・・・」
それから5人ほど知り合いの女を訪ねたが、一言一句同じ会話が繰り返されることとなった。
男は内心喜びながらも、困り果てた表情を作ってから薬屋に戻った。
「ダメだ、おやじ。俺の知り合いにゃあ試せねえ。」
「本当に効くか効かねえかは大して問題じゃねえんだ。それは売り方次第でなんとでもなるさ。問題は人体に悪影響がないかってことなんだ。」
「じゃあ犬とか、なにか動物で試してみるか?」
「それじゃダメだよ、飲むのは人間なんだから。」
「わかったよ、ごちゃごちゃうるさいなあ。だったら作った俺が実験台になってやるよ。」
そう言うと男は白濁した液体を一気に飲み干し、空のコップをテーブルに叩きつけた。
男の名をナルキッソスといった。